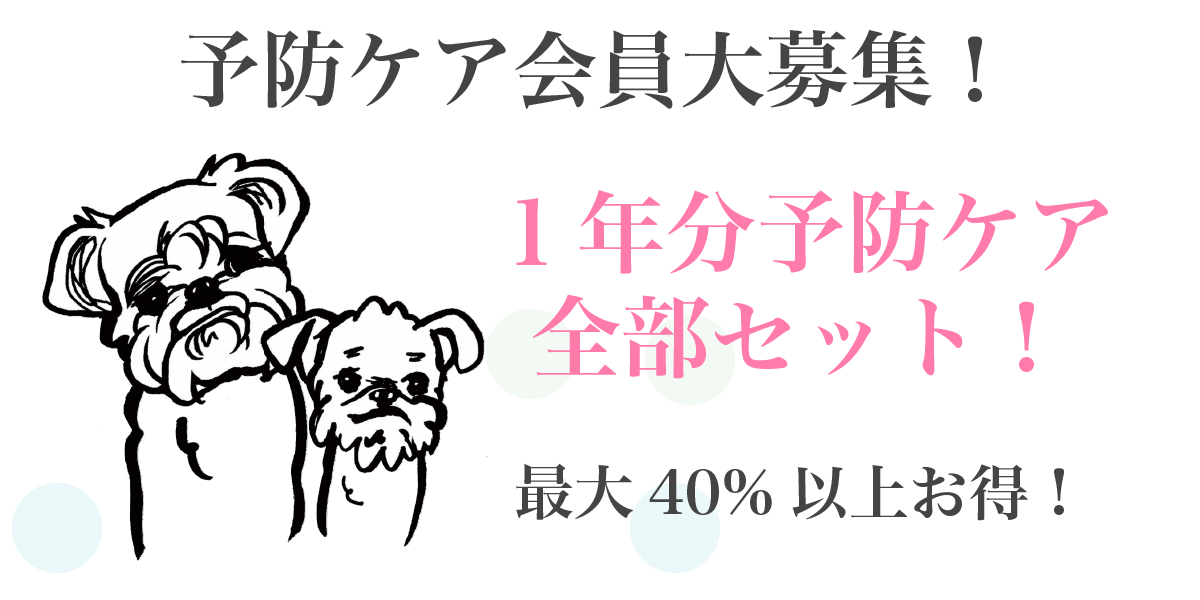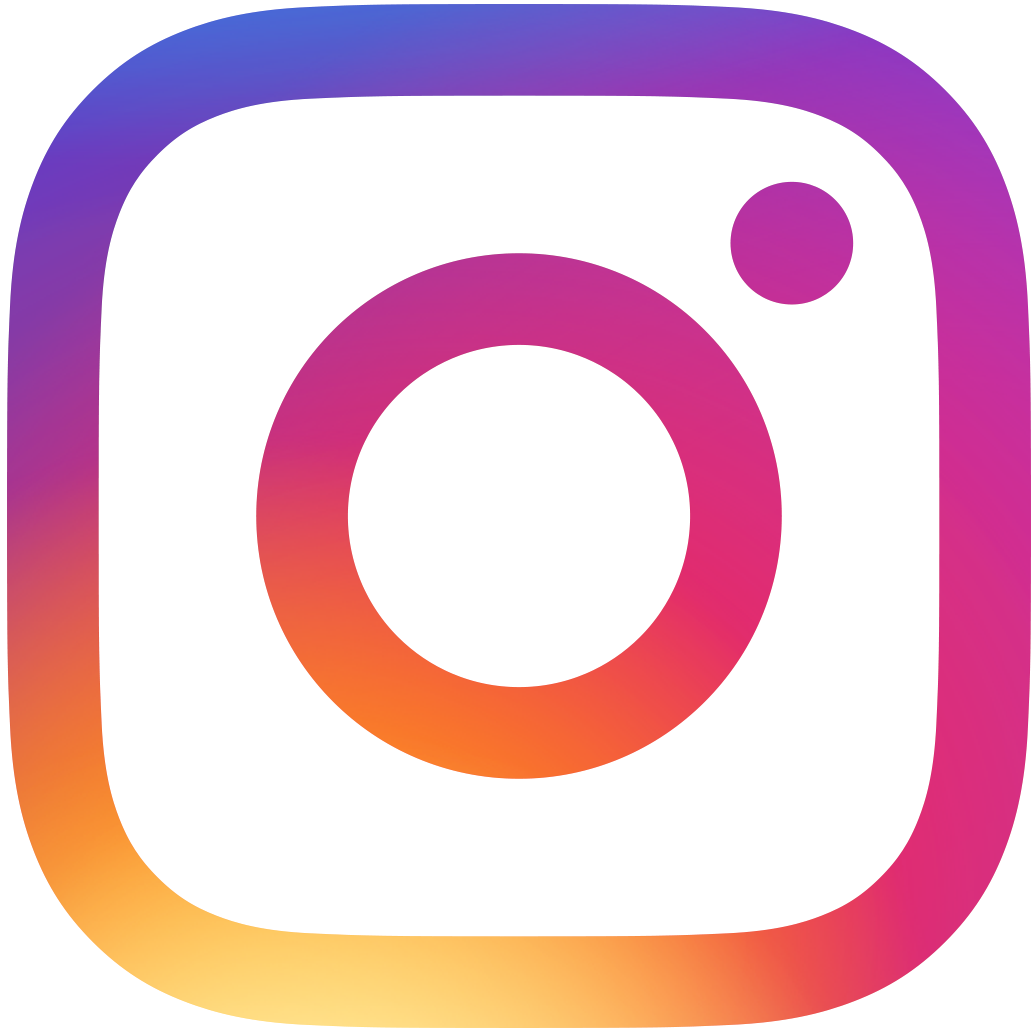愛犬がなんとなく元気がなかったり、体に触れるといつもと違うしこりのようなものを感じたりして、不安になった経験はありませんか?特に中高齢の犬では、体調の変化が深刻な病気のサインであることも考えられます。その一例として「多中心型リンパ腫」が挙げられます。
この病気は、犬の悪性腫瘍の中でも特に発症頻度が高いとされるリンパ腫の一種です。症状がわかりにくく、進行してからようやく気づかれるケースが多いですが、早期発見・治療により長期間元気に生活を続けることができる場合もあります。
今回は犬の多中心型リンパ腫について、診断方法や治療方法予防策、当院で治療を受けた症例などをご紹介します。
犬の多中心型リンパ腫とは
多中心型リンパ腫とはリンパ腫の一種で、主に体表のリンパ節が腫れることが特徴的です。この病気は、リンパ系に属する細胞ががん化し、全身に広がる可能性があります。特に、体表のリンパ節(顎の下、脇の下、股の付け根など)が腫れ、飼い主様が愛犬を触った際にしこりに気づいて来院されることが多いです。
この腫瘍は特に中高齢の犬に多く見られますが、初期段階では目立った症状がないため発見が難しいことが特徴です。
症状
多中心型リンパ腫の初期症状は非常に曖昧です。そのため、飼い主様が愛犬の異変に気づくのは、病気がある程度進行してからというケースがほとんどです。
初期段階では、体調不良や元気・食欲の低下はあまり見られず、唯一のサインが「体表リンパ節の腫れ」である場合が多いです。これに触れると、通常よりも明らかに大きなしこりのように感じられます。
一方で、進行している場合には体調不良や元気・体重の低下、食欲不振といった全身症状が多く見られます。この段階では、腫瘍が他の臓器に影響を与えている可能性も高いため、治療がより複雑になる場合があります。
原因
犬が多中心型リンパ腫を引き起こす詳しい原因は、いまだに完全には解明されていません。ただし、特に10歳以上の中高齢の犬に多く発症することがわかっています。また、遺伝的要因や環境的要因が関与している可能性が指摘されていますが、具体的なリスク要因については研究が進行中です。
診断方法
動物病院では多中心型リンパ腫の診断において、迅速かつ正確な検査を重視します。まずは、体表リンパ節の触診を行い、腫れが確認される場合にはさらなる精密検査を実施します。具体的な検査内容は、以下の通りです。
<細胞診>
体表リンパ節から採取した細胞を顕微鏡で観察し、がん細胞の有無を確認します。
<遺伝子検査>
細胞診だけでは診断が難しい場合、遺伝子検査を行います。この検査では、腫瘍細胞がT細胞(胸腺由来)かB細胞(骨髄由来)かを判別することで、治療方法の選択や予後の予測に役立ちます。
<画像検査>
腫瘍が腹腔内臓器に転移していないかどうかを把握するため、超音波検査(エコー)やX線検査を実施します。悪性腫瘍の転移の影響で体表リンパ節や腹腔内・胸腔内のリンパ節が腫れている場合もあるため、これらの検査による総合的な判断が欠かせません。
治療方法
多中心型リンパ腫の治療には、多剤併用による抗がん剤治療が一般的です。この治療では複数の抗がん剤を組み合わせて使用することで、腫瘍細胞を効果的に抑えます。最初に使用していた抗がん剤が効果を失った場合には、レスキュー療法(別の抗がん剤を使った代替治療)を検討します。
また、多中心型リンパ腫は基本的に手術による治療では効果を発揮しません。リンパ腫は全身に転移しやすいため、1つの腫れたリンパ節を取り除くだけでは十分な効果が得られないからです。
予後
多中心型リンパ腫の治療において、予後は個々のケースにより大きく異なります。しかし、適切な治療を受けることで、愛犬の生活の質(QOL)を向上させ、寿命を大きく延ばせる可能性があります。無治療の場合、多くのケースで寿命は3カ月前後とされていますが、抗がん剤治療を行うことで年単位での延命も期待できます。
抗がん剤の治療を迷う飼い主様が多い理由のひとつに、副作用の心配があります。抗がん剤は副作用を伴うことがありますが、犬の場合は人間ほど強い症状が出ることは稀です。具体的には以下のような副作用が考えられます。
・消化器症状(下痢、嘔吐、食欲不振など)
・血液細胞の低下(好中球の減少、貧血、血小板数の減少など)
・代謝する臓器への影響(腎不全、肝酵素上昇など)
これらの症状が出た場合でも、治療スケジュールを調整したり対症療法を行ったりすることで、ほとんどの場合はコントロールが可能です。また、犬では人間のように毛が抜けたり、強い嘔吐が長期間続いたりすることはほとんどありません。当院では、治療中も愛犬の状態を慎重に見守り、副作用の軽減に努めています。
当院の事例
当院で治療を行った実際の事例をご紹介します。この子は16歳6カ月の去勢済みの犬(シー・ズー)で、もともと僧帽弁閉鎖不全症の治療を続けていました。2023年12月13日に飼い主様が体表リンパ節の腫れや食欲低下に気づき、当院を受診し、診察時に複数のリンパ節の腫れが確認されました。その日のうちに、細胞診を実施するとともに、精度の高い診断のために遺伝子検査を依頼しました。その結果、B細胞性高グレード多中心型リンパ腫であることが判明しました。
この検査結果を受け、2023年12月21日からUW-25プロトコール(多剤併用抗がん剤療法)を開始しました。このプロトコールでは4種類の抗がん剤を併用し、現在まで(約13カ月間)明らかな副作用は見られず、リンパ節の腫れも消失しました。また、全身への転移もなく、食欲や活力も維持されています。
予防法やご家庭での注意点
多中心型リンパ腫は、早期発見が治療の成否を左右します。そのため、ご家庭では普段から愛犬とスキンシップをとり、体表リンパ節の状態を確認してください。特に顎の下や脇の下、股の付け根などはリンパ節が集中している部位であるため、腫れや違和感がないかをチェックしましょう。
また、愛犬の食欲や活力に変化がある、体表リンパ節が腫れているといった症状を発見したら、早めに動物病院を受診してください。
まとめ
犬の多中心型リンパ腫は、中高齢の犬に多く見られる悪性腫瘍の一つです。症状がわかりにくいため、発見が遅れることもありますが、早期発見と治療によって愛犬のQOLを向上させ、寿命を延ばすことが可能です。
当院では、症状に応じた精密な検査と最適な治療方法を提供し、飼い主様と協力して愛犬の健康を守ることに尽力しています。少しでも気になる症状が見られた場合は、お気軽にご相談ください。
東京都調布市の動物病院なら『タテイシ動物病院』
【当院のアクセス方法】
府中市・三鷹市・狛江市アクセス良好です。
■電車でお越しの場合
・京王線 調布駅 東口 徒歩5分
・京王線 布田駅 徒歩5分
■バスでお越しの場合
布田一丁目バス停から徒歩1分
■車でお越しの場合
調布ICから車で6分
病院隣に当院専用駐車場2台あります。
※満車時はお会計より近隣パーキング料金(上限あり)をお値引きいたします。