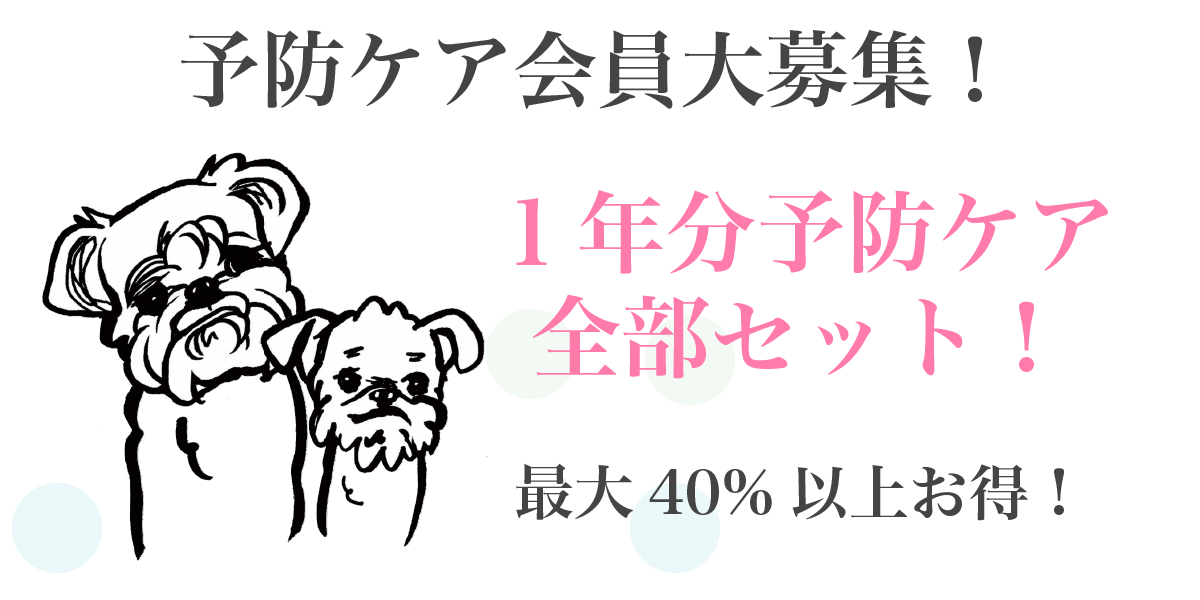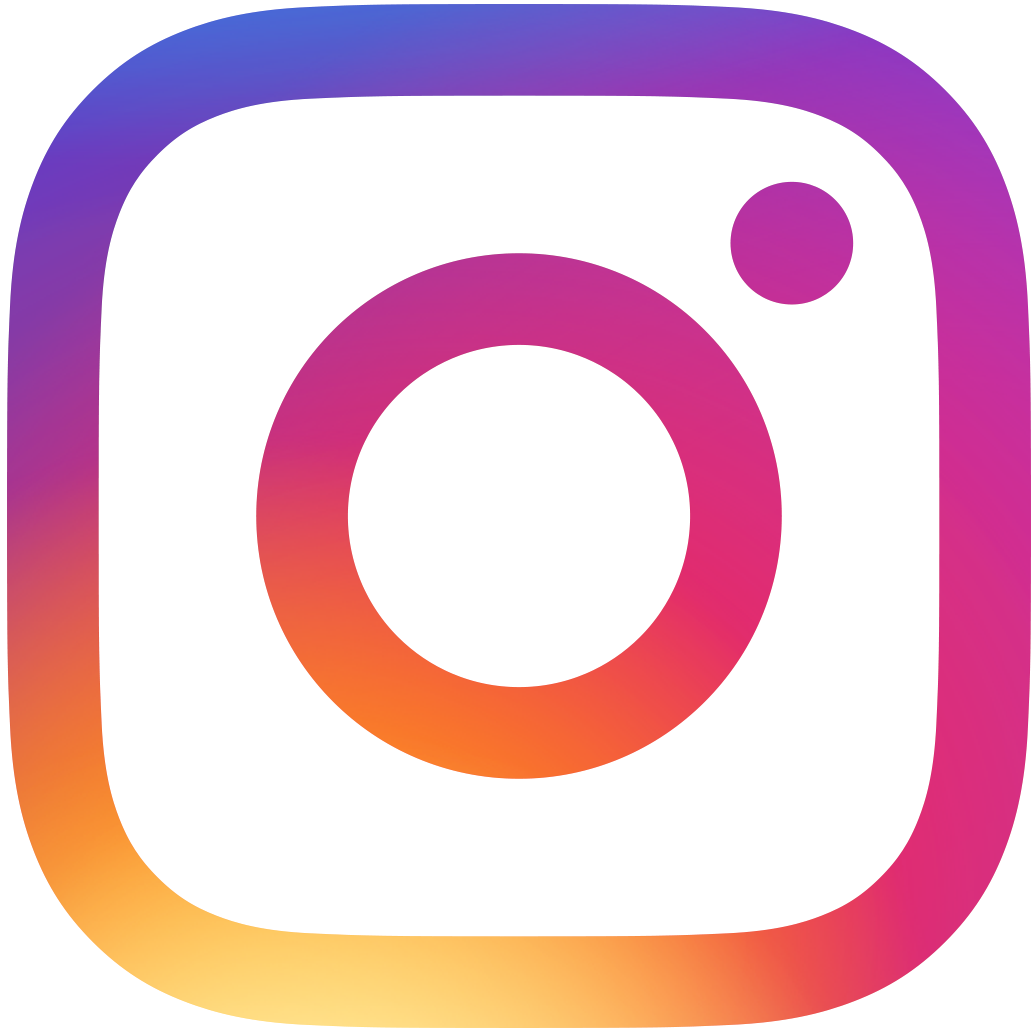子宮蓄膿症は、避妊をしていないメスの犬や猫に発症する病気のひとつです。避妊手術(卵巣子宮摘出術)をしていれば発症しないことから、大きな病気と思われない方も多いですが、実際は発症すると命の危険に関わることもあります。
特に犬では婦人科系疾患の発生率が高く、人間の婦人科系疾患と比べて非常に多いとされています。実際、動物病院では「避妊しておけばよかった…」と後悔の声を耳にすることも少なくありません。
子宮蓄膿症は早期発見・早期治療によって救命できる可能性が高まりますが、そのためには飼い主様が病気の存在を知っておくことが重要です。
今回は犬と猫の子宮蓄膿症の症状や診断方法、治療方法、そして当院が実際に行っている対応について詳しくご紹介します。
子宮蓄膿症とは?特徴と症状
子宮蓄膿症とは、未避妊のメス犬やメス猫の子宮内で細菌感染が起こり、内部に膿がたまってしまう病気です。特に犬においては産科系(繁殖系)の中でも多く見られます。
この病気は発症に気付きにくいこともあるため、重症化した場合、敗血症や血栓傾向になりやすく、命にかかわることも多いです。犬や猫は言葉で症状を訴えられないため、飼い主様の気づきが命を救う鍵となります。
<子宮蓄膿症のタイプと症状>
子宮蓄膿症には大きく分けて「開放型」と「非開放型(閉鎖型)」2つのタイプがあります。
■開放型
陰部から膿が排出されるため、比較的早期に発見しやすい特徴があります。開放型は陰部から膿が出る、下痢、元気消失、食欲不振といった症状が見られます。
■非開放型(閉鎖型)
膿が外部に排出されず、体内に蓄積してしまうため、気づきにくく重篤化しやすいことが特徴的です。初期には下痢や腹部の張り、多飲多尿などが見られます。病気が進行すると細菌が全身状態に悪影響を及ぼし、ショック状態や衰弱、稀に子宮が破裂するといった致命的な状態に陥ることもあります。
診断方法
子宮蓄膿症が疑われる際、当院では以下のようなステップで診断を行います。
①性別と避妊歴、症状などの確認
未避妊のメスで、上記のような症状があるかを確認します。
②血液検査
白血球の数値の上昇やCRPやSAAといった炎症マーカー(炎症に反応する数値)の上昇が見られるかを確認します。
③エコー検査(超音波検査)
特に重要なのがエコー検査です。子宮の肥大や内部の液体貯留の有無を精密に確認できます。
また、子宮が膨らんでいても、必ずしも子宮蓄膿症とは断定することはできず、子宮蓄膿症と似たような所見を呈するほかの疾患(子宮水腫、子宮内膜炎など)もあるため、他の疾患との鑑別も慎重に行います。そのため、エコーの画像だけでなく、臨床症状や血液検査のデータを総合的に評価して診断を下します。
治療方法
子宮蓄膿症と診断された場合、基本的には外科手術を行います。手術では、膿の原因である子宮と卵巣そのものを摘出する「卵巣子宮摘出術(避妊手術)」を実施します。
内科的治療も選択肢としては存在しますが、それだけでは完治が困難であり、再発のリスクも高いため、根本的な解決を目指すには外科手術が不可欠です。
ただし、犬や猫の全身状態が悪化している場合には、すぐに手術ができないこともあります。当院では術前の全身評価を徹底して行い、必要に応じて点滴による脱水補正や抗生物質の投与などを行い、手術に耐えられる状態まで慎重に整えます。
中には、体温低下や血圧低下といった症状が出ている場合もあり、このような重症例では手術自体のリスクも高まります。そのため、状態に応じた慎重な術前管理が必要になります。
また、高齢や全身状態が悪いなどの理由で麻酔をかけられないと判断された場合は、子宮から膿を排泄させる薬(アグレプリストン)を抗生剤と併用して使用する場合があります。(ただし、開放型に限ります)
術後の管理
術後は慎重な経過観察が必要です。感染や出血などの合併症が起きていないかを注意深くモニタリングし、全身状態が安定していることを確認してから退院の判断を行います。
食事の再開も段階的に行い、無理のない範囲で体調を戻していきます。ご自宅に戻ってからもしばらくは安静が必要で、急な運動によって出血などのトラブルが起こらないよう、適切な休息と運動制限をお願いしています。
経過と注意点
子宮蓄膿症は、発見のタイミングがその後の経過を大きく左右します。特に、体温が低い、立てない、血圧が下がっているなどの全身状態が悪化している場合は、手術を行っても合併症(血栓症、多臓器不全など)で命を落とすリスクがあるほど危険な状態です。
さらに重症化している場合、麻酔すら困難で手術自体ができないケースもあります。こうした事態を避けるためにも、早期発見と早期の対応が何よりも大切です。
予防法
子宮蓄膿症は、若いうちに避妊手術(卵巣子宮摘出術)を行えば100%予防できる病気です。
避妊手術は、子宮蓄膿症の予防だけでなく、乳腺腫瘍や卵巣腫瘍といった他の重大な病気の予防効果もあります。また、マーキングなどの問題行動の改善にも効果があります。
特に避妊を行っていない犬や猫に関しては、定期的な健康診断を受けることが大切です。少しでも気になることがあれば、早めに獣医師に相談しましょう。
治療成績と予後
子宮蓄膿症は、早期に発見し適切な治療を行えば完治することが可能な病気です。しかし、発見が遅れて全身状態が極度に悪化したケースなどの重症例では命に関わることもあります。
そのため、若いうちに避妊手術を行うことがなによりも大切です。
まとめ
子宮蓄膿症は、発見が遅れると命に関わる深刻な危険な病気です。しかし、避妊手術(卵巣子宮摘出術)という確実な予防法が存在します。「うちの子はまだ大丈夫」と思っている間に症状が進行してしまうこともあるため、少しでも心配なことがあれば、早めの受診をおすすめします。
犬の産科系疾患の発生率は人よりもはるかに高く、避妊手術を行っていれば防げる病気がたくさんあります。大切な命を守るために、避妊手術という選択肢を前向きにご検討ください。
■関連する記事はこちらから
東京都調布市の動物病院なら『タテイシ動物病院』
【当院のアクセス方法】
府中市・三鷹市・狛江市アクセス良好です。
■電車でお越しの場合
・京王線 調布駅 東口 徒歩5分
・京王線 布田駅 徒歩5分
■バスでお越しの場合
布田一丁目バス停から徒歩1分
■車でお越しの場合
調布ICから車で6分
病院隣に当院専用駐車場2台あります。
※満車時はお会計より近隣パーキング料金(上限あり)をお値引きいたします。