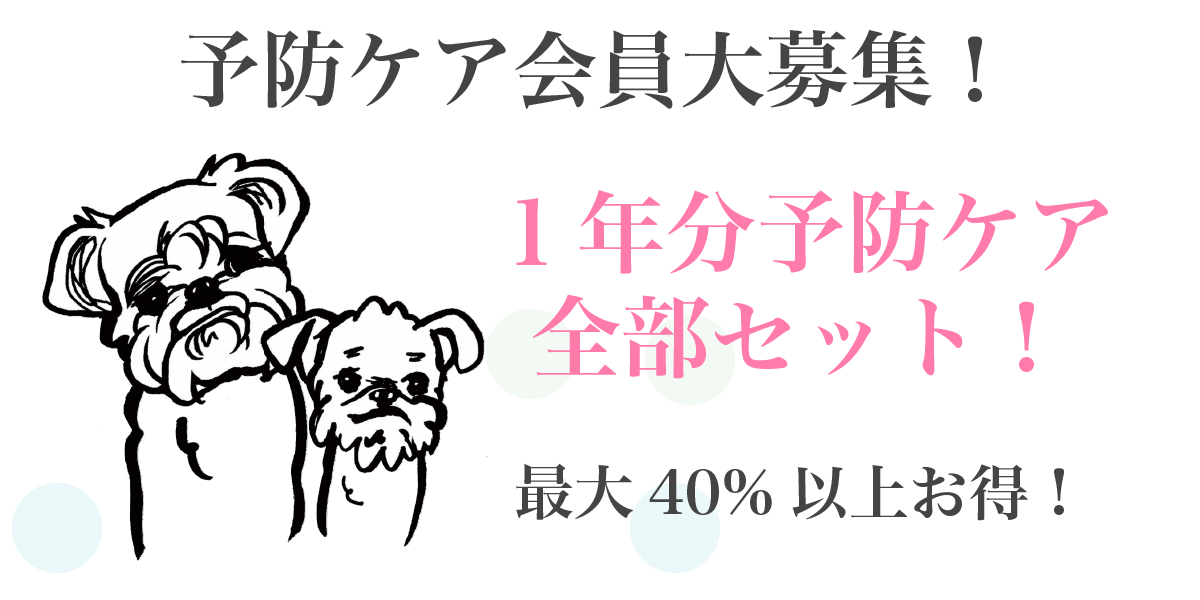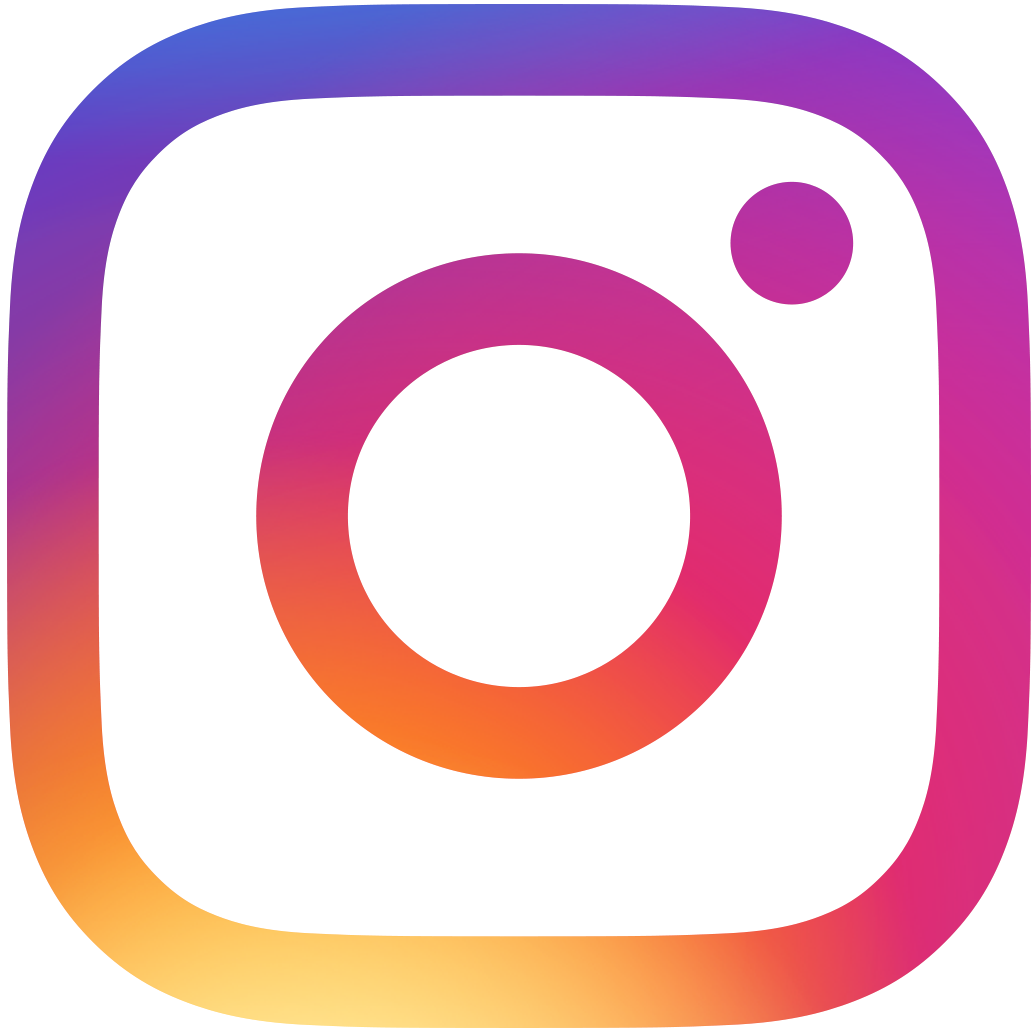最近、愛猫が「水をたくさん飲むようになった」「おしっこの量が多い」「毛がパサついてきた」そんな変化を感じたことはありませんか?これらの症状は、猫の糖尿病のサインかもしれません。
猫の糖尿病は、犬とは発症のしくみが異なる点が多いため、治療や管理方法も変わってきます。そのため、猫特有の症状や病態を正しく理解し、適切な診断と治療を行うことが大切です。
今回は猫の糖尿病について、当院で行っている診断や治療方法、さらにはご家庭での注意点など、飼い主様が知っておきたいポイントについてご紹介します。
猫の糖尿病とは?
猫の糖尿病は、血糖値を下げる働きを持つホルモン「インスリン」がうまく作用しなくなることで、慢性的な高血糖状態が続く病気です。
猫では、インスリン自体は分泌されているにもかかわらず、体の各組織がインスリンの働きに反応しにくくなる「インスリン抵抗性」が主な原因とされており、いわゆるⅡ型糖尿病に分類されることが多くなっています。
一方で犬の糖尿病は、インスリンの分泌そのものができなくなるⅠ型がほとんどであり、猫とは病態や治療方針が異なります。
原因
猫の糖尿病の主な原因としては、肥満や運動不足といった生活習慣の影響が大きいといわれています。体脂肪が増えると、インスリンがうまく働かなくなってしまうことがあります。その結果、体の中の代謝バランスが乱れ、糖尿病を引き起こすきっかけになると考えられています。
また、脂質代謝の悪い猫も糖尿病発生のリスクが高まるため、基礎疾患として何らかの脂質代謝が悪くなる要因がある場合、肥満でなくても糖尿病になります。そのため、基礎疾患の把握も重要になります。
症状・診断方法
当院ではまず、飼い主様から日常生活で見られる症状について丁寧にお話を伺います。
特に、以下のような変化が見られる場合は、糖尿病の可能性があります。
<・多飲多尿
・食べているのに痩せてきた
・毛づやが悪くパサパサしてきた
・目が落ち、くぼんで見える
こうした症状がある場合には、次のような検査を実施し、糖尿病の有無を確認します。
<血液検査>
血液中のブドウ糖(グルコース)の濃度を測定します。正常よりも高い値が出た場合は過緊張状態または興奮ストレス、高血糖が疑われ、糖尿病の可能性も出てくるため、下記の尿検査やフルクトサミン測定などを行います。
<尿検査>
尿中に糖が含まれていないかを確認します。血糖値が一定以上になると、尿にも糖が漏れ出てくるため、糖尿病の判断材料になります。あまりに高血糖状態が続いた場合、ケトン体という毒素が出ていないかもチェックします。
<フルクトサミン測定>
過去1〜2週間の平均的な血糖値を測定する検査です。一時的なストレスによる高血糖と慢性的な糖尿病を見分けるために役立ちます。
なお、多くの動物病院ではこれらの検査を外部の検査機関に依頼しますが、当院では院内で迅速に測定可能です。そのため、診断から治療開始までをスムーズに進めることができます。
治療方法
猫の糖尿病治療は、基本的にインスリン注射による血糖値のコントロールが中心です。ただし、猫は犬よりも脱水状態で来院することが多いため、まずは静脈点滴や皮下点滴で水分バランスを整えるところから始めます。
脱水が改善されたら、インスリンを少量から投与し、1日の血糖値の変化をグラフ化した「血糖曲線」をもとに最適な量を見極めていきます。血糖曲線は、治療方針を決めるうえで非常に重要な情報です。
インスリンにはいくつか種類があり、作用時間や効き方に違いがあります。当院では、猫の体調や生活スタイルに応じて、最適な製剤を選択しています。
糖尿病と診断された猫には、毎日インスリン注射が必要です。初めての方には不安もあるかと思いますが、ご安心ください。当院では、注射の方法やコツ、気をつけるポイントなどを丁寧にご説明し、飼い主様と一緒に治療を進めてまいります。
<経口薬という新たな選択肢>
近年では「センベルゴ(有効成分:ベラグリフロジン)」という猫専用の経口薬も登場しています。この薬はインスリンを使用せずに血糖値をコントロールすることが可能な新しい選択肢です。
ただし、効果が出にくい猫も一部いること、血糖値は上がらなくても「糖尿病性ケトアシドーシス」になるリスクがあることには注意が必要です。
糖尿病性ケトアシドーシスとは、高血糖状態が続くことで肝臓からケトン体という毒素が分泌され、嘔吐や脱水、昏睡などを引き起こす重篤な症状のことです。命に関わることも多く、センベルゴを使用する場合でも、インスリン治療と同様に定期的な受診や血液検査、ケトン体の測定が欠かせません。
センベルゴを使用した場合、結果として来院の頻度を減らすことができる可能性が高く、日常的に行わなければならない血糖曲線のチェックもほぼ不要になります。
注射が苦手な猫や、毎日の投与に不安がある飼い主様にとっては、有効な選択肢のひとつとなり得ます。
当院では、こうした新しい治療法についても丁寧にご案内しており、常時血糖値をモニタリングできるセンサー機器(リブレ)や、飼い主様ご自身で血糖値を確認できる簡易測定器の貸し出しも行っています。ご希望やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
治療後の予後
猫の糖尿病は、インスリン治療が必要な病気ではありますが、適切な治療と生活管理によって、良好な状態を保てるケースも多くあります。実際に、治療の初期にはインスリン注射が必要だったものの、その後体調が安定し、最終的に注射を卒業できた猫も多いです。
こうした経過は、猫に多く見られる「Ⅱ型糖尿病」の特徴のひとつです。人間の生活習慣病と同様に、食事内容や生活環境を見直すこと、基礎疾患をコントロールすることで、症状の改善が期待できる病気でもあります。
ただし、猫は犬と違って「ゆっくりと時間をかけて食事をとる」「食事の時間が一定でない」といった傾向があり、それによって血糖値のコントロールが難しくなることもあります。このような状況が続くと、脱水や糖尿病性ケトアシドーシスなどの重篤な合併症を引き起こし、命に関わるリスクも高まります。
特に猫ではケトアシドーシスの発症率が犬よりも高いとされており、悪化のスピードも速い傾向があります。そのため、症状が安定しているように見える場合でも、定期的な通院と血液検査によるチェックは欠かせません。
当院でも、飼い主様と二人三脚で治療を続け、インスリンを離脱しつつ血糖値を安定させている猫たちが多くいます。日々の管理は大変なこともありますが、一歩ずつ着実に改善へつなげていくことが大切です。
不安なことや気になる点があれば、いつでもご相談ください。
予防法やご家庭での注意点
猫の糖尿病は、現時点では完全に予防する方法が確立されていませんが、以下のような日々の生活習慣を見直すことで発症のリスクを下げることが可能です。
<食事の見直し>
高カロリーなフードやおやつの与えすぎは肥満につながり、糖尿病の発症リスクが高まります。年齢や体型、運動量に合ったバランスのよいフードを選び、必要に応じて療法食などの活用も検討しましょう。
<適度な運動>
室内飼いの猫はどうしても運動不足になりがちです。お気に入りのおもちゃやキャットタワーを活用しながら、毎日少しでも体を動かす時間をつくってあげましょう。
適度な運動はインスリンの効きをよくさせるという報告があり、ストレスの軽減にもつながり、心身の健康維持に役立ちます。
そして何より大切なのは、早期発見と早期対応です。「最近ちょっと様子が変かも」と感じた時点で、すぐにご相談ください。小さな違和感が、大きな病気のサインであることもあります。
まとめ
猫の糖尿病は、生活習慣が影響するⅡ型糖尿病が多く、犬のⅠ型糖尿病とは異なる特徴があります。脱水症状が強く出やすいこと、インスリン治療を継続しなくてもよくなる可能性があること、そしてケトアシドーシスのリスクが高いことなど、猫特有の注意点を理解しておくことが大切です。
当院では、インスリンや経口薬による治療だけでなく、血糖曲線の作成やリブレ(血糖測定センサー)の装着、飼い主様への丁寧なご説明などを通じて、安心して治療に向き合える体制を整えています。
愛猫の健康を守るうえで、日々の小さな変化に気づくこと、そして飼い主様のご協力が何より大切です。どんな小さな不安でも構いませんので、気になることがあればいつでもご相談ください。
★ご予約は下記のLINE予約フォームから!★
東京都調布市の動物病院なら『タテイシ動物病院』
【当院のアクセス方法】
府中市・三鷹市・狛江市アクセス良好です。
■電車でお越しの場合
・京王線 調布駅 東口 徒歩5分
・京王線 布田駅 徒歩5分
■バスでお越しの場合
布田一丁目バス停から徒歩1分
■車でお越しの場合
調布ICから車で6分
病院隣に当院専用駐車場2台あります。
※満車時はお会計より近隣パーキング料金(上限あり)をお値引きいたします。
<参考文献>