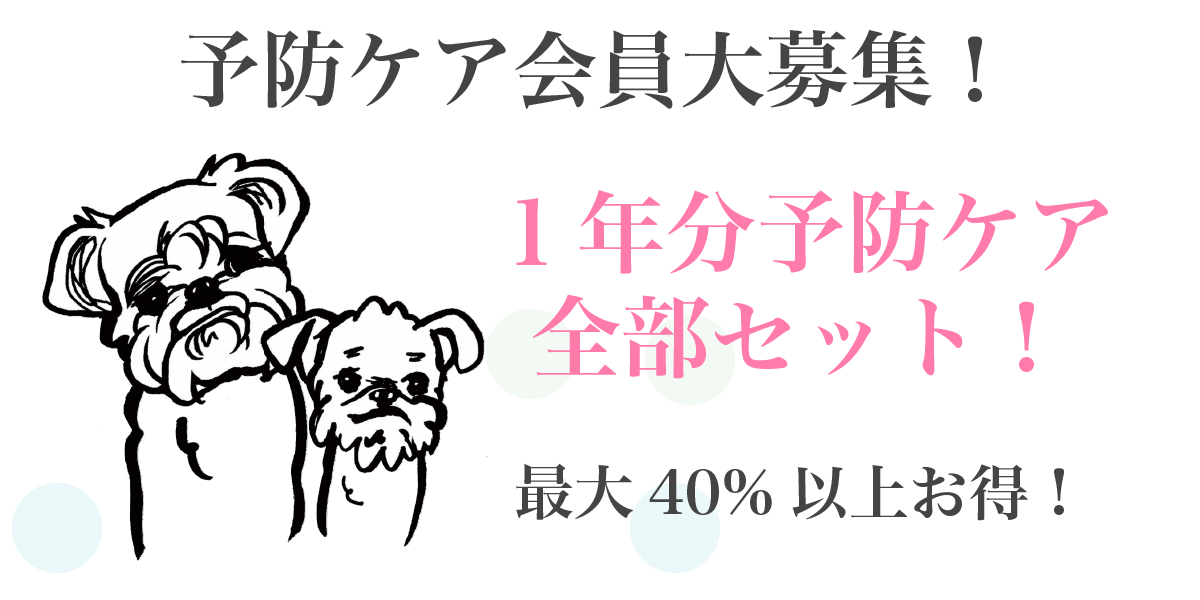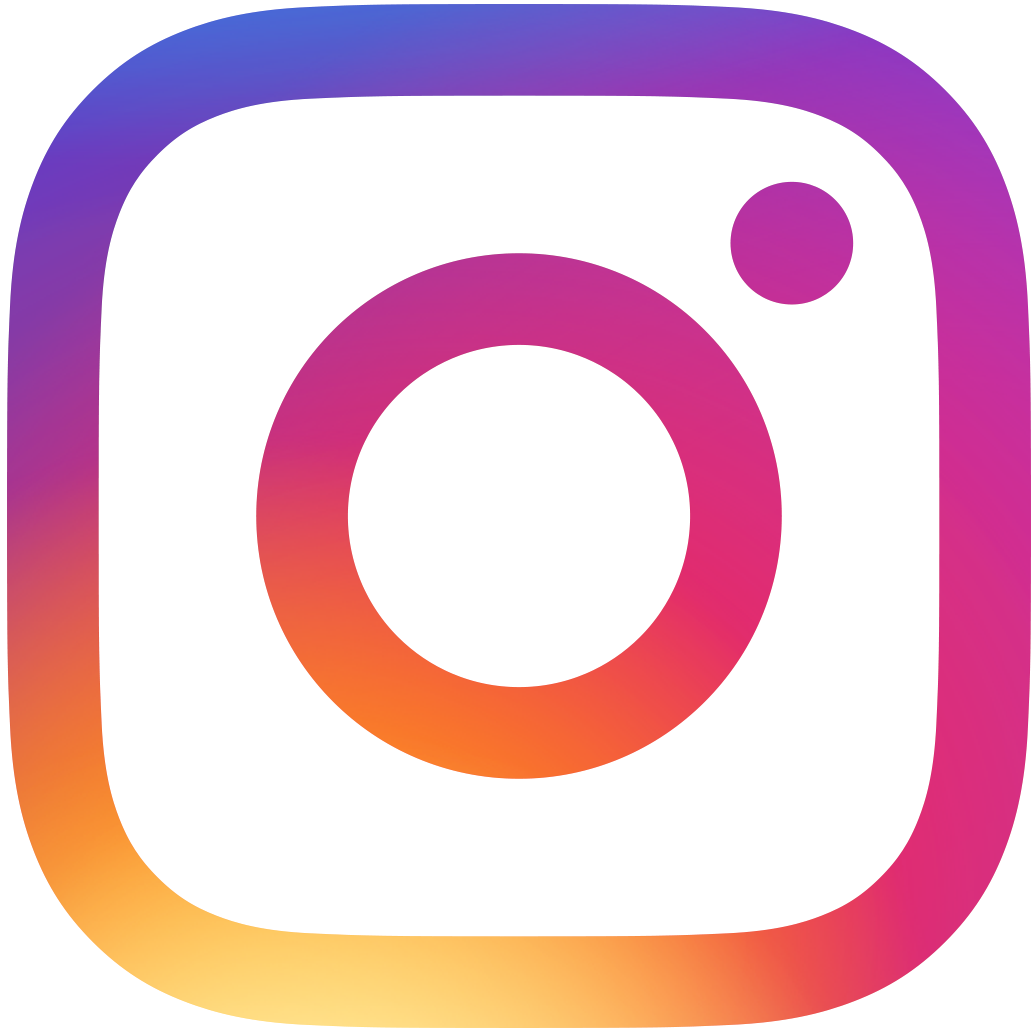愛猫が「年を重ねても見た目は元気そうだから安心」と感じたことはありませんか?シニアになっても活発で食欲もある猫は、一見とても健康そうに見えます。しかし、もし「食べているのに痩せてきた」「以前より落ち着きがない」といった様子が見られたら、それは甲状腺機能亢進症という病気のサインかもしれません。
この病気は猫に多く見られ、腎不全や腫瘍に次いで発症頻度の高い疾患です。治療をせずに放置すると、全身の臓器に負担がかかり、命に関わることもあるため注意が必要です。
当院では、このような病気に対して迅速に対応できるよう、院内にホルモン測定機器を完備しています。外部検査機関に依頼せずともその場で結果をお伝えし、すぐに治療を開始することができます。
そこで今回は猫の甲状腺機能亢進症について、当院での診断方法や治療方法、予後や管理などを解説します。
猫の甲状腺機能亢進症とは?
猫の甲状腺機能亢進症とは、甲状腺から分泌されるホルモン(T4)が過剰に分泌されることで、全身の代謝が異常に活発になる病気です。
特に高齢の猫でよく見られ、以下のような症状が現れます。
・よく食べるのに体重が減る
・攻撃的になったり、性格が変わったりする
・落ち着きがなくなる
このような変化が見られても、普段と変わらず元気そうに見えるため、見過ごされてしまうケースも少なくありません。実際に当院でも、健康診断の際に偶然見つかることがあります。
また、8歳を過ぎると甲状腺機能亢進症だけでなく、腎不全や他の慢性疾患を発症するリスクも高まります。そのため、定期的な健康診断がとても重要です。
猫の慢性腎不全の症状や当院ならではの治療方法についてより詳しく知りたい方はこちら
犬や猫の腎不全の症状や予防法、ご家庭での注意点についてより詳しく知りたい方はこちら
診断方法
甲状腺機能亢進症の診断には、「甲状腺ホルモン(T4)の測定」が必要不可欠です。一般的な動物病院では外部の検査機関に検体を送るため、結果が出るまで数日かかることがあります。
しかし当院では、T4を含むホルモン検査を院内で即日実施できる体制を整えています。そのため、検査当日に数値を把握でき、飼い主様に結果をご説明した上で、その日のうちに治療のご相談まで進めることが可能です。
また、甲状腺の状態をより詳しく把握するために、超音波(エコー)検査により甲状腺の大きさや内部構造も確認します。さらに、甲状腺機能亢進症と深く関わる腎臓の状態(BUNやクレアチニンなど)も同時に血液検査で評価し、全身の健康状態を総合的に診断します。
治療方法
治療では、主に「抗甲状腺薬(メルカゾール)」を用いた内科療法が選択されます。この薬は甲状腺ホルモンの合成を妨げ、ホルモン濃度を正常範囲内にコントロールする役割があります。
治療初期は、ホルモン値が変動しやすいため、2週間から1か月に1回のペースで、甲状腺ホルモンの値をモニタリングしていく必要があります。治療が安定してくれば、来院頻度を徐々に調整していくことも可能です。
また、治療を始めると、これまで目立たなかった腎臓の異常が見つかることも少なくありません。そのため、治療中も定期的に腎臓の数値を確認することがとても重要です。これにより、合併症を早期に把握し、症状の進行を防ぐことができます。
なお、治療は生涯にわたる投薬管理が必要となりますが、きちんと管理を続けることで快適な生活を維持できます。
治療における重要な注意点
甲状腺機能亢進症の治療では、投薬を自己判断で中断したり、量を変更したりすると、合併症を引き起こすことがあります。特に注意すべきなのが、「甲状腺クリーゼ」と呼ばれる急性の甲状腺中毒です。
これは、甲状腺ホルモンが一気に過剰に分泌されることで、全身の臓器が次々と機能不全に陥る命に関わる状態です。以下のような症状が見られたら、一刻も早く動物病院を受診してください。
・頻呼吸:急に呼吸が荒くなる
・頻脈・不整脈:脈が速く、不規則になる
・発熱:体が熱くなる
・呼吸困難:息苦しそうにする、口を開けて呼吸する
・視力の異常:動かない、物にぶつかる
・神経症状:けいれん、呼びかけに反応しない
このような症状は突然現れることが多いため、重篤な状態に陥る前に予防的な管理が非常に重要です。
予後と長期管理
甲状腺機能亢進症は完治が難しい疾患ですが、ホルモン値を適切に管理することで、これまでと変わらない生活を送ることも十分可能です。
治療を始めた後も、定期的な血液検査によるホルモン値の確認や、日々の投薬管理が必要です。また、腎臓など他の臓器への影響を早期に察知するためにも、全身の健康状態を継続的に確認することが大切です。
この病気は一時的なものではなく、「生涯にわたってケアしていく」ことが求められます。だからこそ、飼い主様のご理解と日々のサポートが、愛猫の健康を守るうえでとても大きな力になります。
予防と早期発見
甲状腺機能亢進症を完全に予防することは難しいですが、早期発見によって重症化を防ぐことは十分に可能です。
特に、8歳以降の猫では他の慢性疾患も併発しやすくなるため、年に1回の血液検査を含む健康診断の受診をお勧めします。さらに、11歳以降のシニア期に入った猫では、年に2回の健康診断の受診を推奨します。
また、健康診断に加えて、日常生活では以下のような変化がないかをこまめにチェックしましょう。
・食欲や体重の変化
・落ち着きのなさや性格の変化
「いつもと少し違う」と感じた際は、様子を見ずに、早めに動物病院にご相談ください。
まとめ
猫の甲状腺機能亢進症は、命に関わる深刻な疾患です。しかし、適切な診断と治療、そして継続的な管理によって、穏やかで快適な日常を取り戻すことができます。
当院では、院内で迅速にホルモン測定を行える環境を整えており、診断から治療までをスムーズに進めることが可能です。シニア猫の健康を守るためにも、少しでも気になる症状がありましたら早めにご相談ください。
★ご予約は下記のLINE予約フォームから!★
東京都調布市の動物病院なら『タテイシ動物病院』
【当院のアクセス方法】
府中市・三鷹市・狛江市アクセス良好です。
■電車でお越しの場合
・京王線 調布駅 東口 徒歩5分
・京王線 布田駅 徒歩5分
■バスでお越しの場合
布田一丁目バス停から徒歩1分
■車でお越しの場合
調布ICから車で6分
病院隣に当院専用駐車場2台あります。
※満車時はお会計より近隣パーキング料金(上限あり)をお値引きいたします。