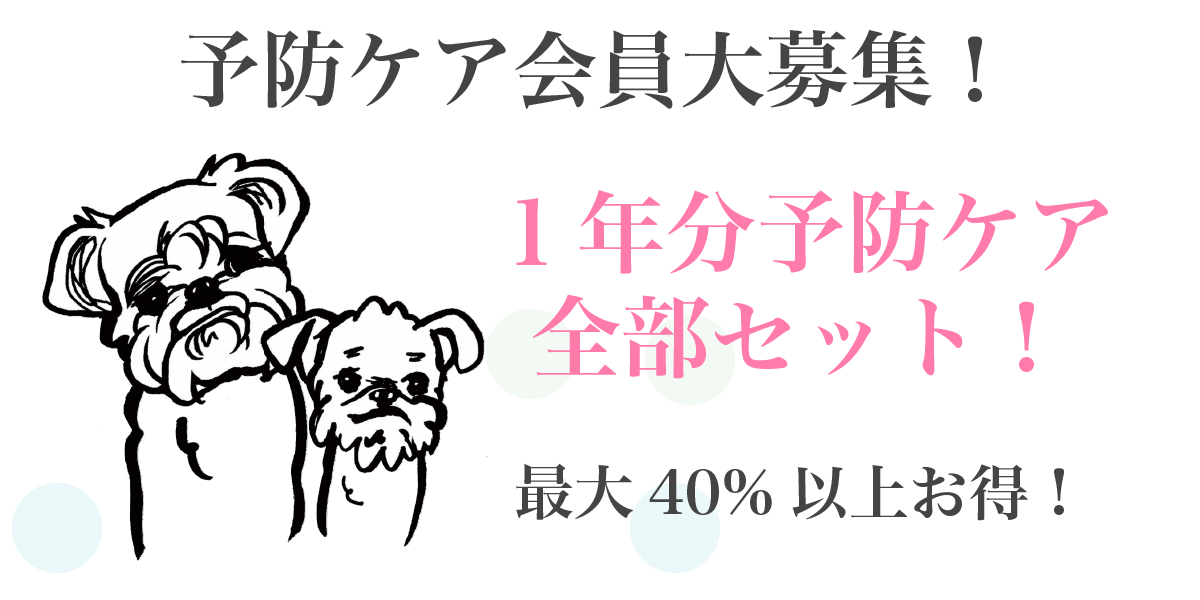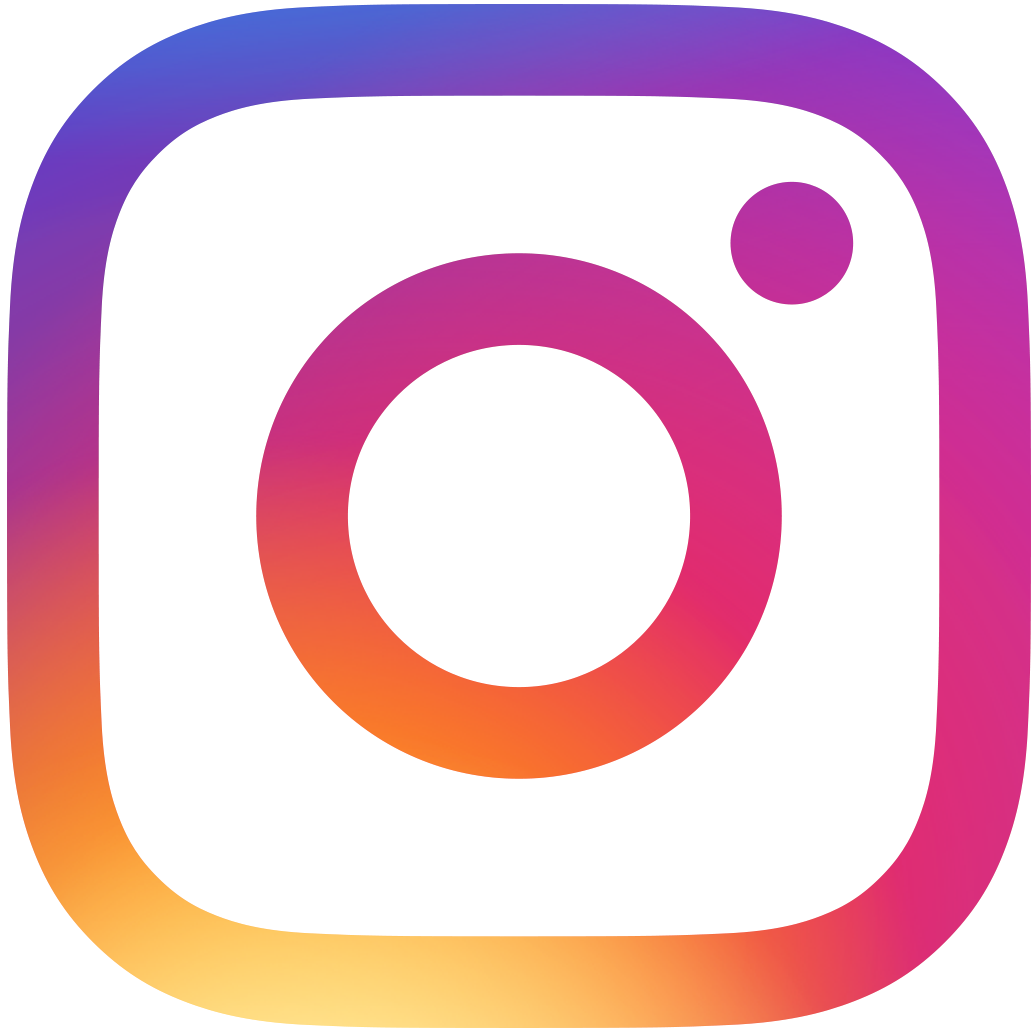突然、犬や猫の意識がなくなったり、体が硬直して倒れ込んだりする様子を目の当たりにしたとき、飼い主様は「どう対処すればいいの?」と強い不安や恐怖を感じるのではないでしょうか?「このまま命に関わるのでは…」「すぐに病院に行くべきなのか…」と混乱してしまうお気持ちはとてもよく分かります。
犬や猫の発作にはさまざまな原因があり、その中には「てんかん」も含まれます。てんかんと聞くと、完治が難しい病気という印象を持たれるかもしれませんが、実際には多くのケースで発作の頻度や重症化を抑えることが可能です。正しく観察し、適切な診断と治療を受ければ、発作と上手に付き合いながら生活を送ることができます。
今回は、発作が起きたときの正しい対応法や考えられる原因、診断や治療の流れについて、調布市にあるタテイシ動物病院が実際に行っている対応をもとに詳しくご紹介します。
犬や猫の発作とは?代表的な症状
犬や猫が発作を起こすと、以下のような症状がよく見られます。
・意識がもうろうとする、または完全に失う
・手足の硬直や痙攣
・よだれを大量に垂らす
・おしっこやうんちを漏らす(失禁)
その他にも、「手を上げるだけ」「ひっくり返るだけ」といった異常行動だけを示す部分発作(焦点発作)というケースもよくあります。
発作の多くは数十秒から数分程度で自然に収まります。短時間で終わる発作であれば、慌てず様子を見ることが大切です。しかし初めて発作を目にした場合、飼い主様はとても驚かれることと思います。
そのような中で、「これは本当に発作なのか?」と迷うケースもあります。実際には、発作とよく似た症状であっても、まったく別の原因によって起こっている場合もあり、注意が必要です。
「発作」と似た症状としては、以下のようなものもあります。
<失神>
主に心臓や血圧の異常が関係しており、突然バタンと倒れてケロッと立ち上がるのが特徴です。
<前庭疾患>
内耳・中耳や脳の異常によって引き起こされ、首を傾げたり目が揺れたり、まっすぐ歩けないなど症状が現れます。
これらは神経系に関連する症状ではありますが、発作とは異なるため、動物病院での正確な見極めが必要です。
発作の主な原因
発作の原因は、主に以下が挙げられます。
<代謝性疾患>
血液中の成分バランスが崩れると、脳に異常な信号が送られ、それが発作の引き金となることがあります。たとえば、腎不全の末期に見られる尿毒症による中毒や、低血糖、カルシウムやナトリウムといったミネラルバランスの異常、肝臓から代謝されるべきアンモニアの毒素が高くなり脳障害を起こすなどが原因となることがあります。
これらの異常は血液検査で明確に確認できることが多いため、発作の診断においては最初に行うべき重要な検査項目となります。
猫の腎臓ケア、今から始めませんか?慢性腎不全の基礎知識はこちらからご覧いただけます
<中枢神経系の疾患>
脳炎や脳血栓、脳出血、脳腫瘍、先天性の脳の奇形などが原因となることがあります。特に症状が進行性である場合や、発作以外にも行動異常が見られる場合には、こうした疾患を疑って精密検査(MRI)が必要になります。
<特発性てんかん>
上記の検査を行った上で明らかな異常がない場合は、特発性てんかん(原因不明の発作)と診断されます。特に犬ではこの特発性てんかんの割合が高く、2~6歳くらいで初発するケースが多く見られます。
発作が起きたときの対応
発作が起こると、突然のことで驚き慌ててしまうかもしれませんが、まずは飼い主様自身が冷静になることが重要です。
発作中の犬や猫は脳への刺激があると、より発作が止まらなくなってしまう可能性があるため、大声で呼びかけたり、体を揺さぶったりすることは避けましょう。また、周囲の家具に頭や体をぶつけてケガをしないよう、安全を確保することが大切です。
可能であれば発作時の様子を動画で記録しておくことをおすすめします。発作の持続時間や身体の動き、種類などを正確に把握できるため、診断や治療方針を立てるための大きな助けになります。
なお、発作が数分以内におさまり、その後しっかりと回復している場合でも、なるべく早めに動物病院を受診しましょう。
すぐに受診すべきケース
以下のようなケースでは緊急性が高いため、すぐに動物病院へ連絡してください。
・発作が5分以上続く
・意識が戻らないまま、次の発作がすぐに起こる
・1日に複数回、連続して発作が起こる
このような状態を「重積発作」といい、神経に深刻なダメージを与えるだけでなく、命に関わる可能性もあります。こうした緊急時には、当院でもすぐに酸素吸入や静脈点滴、鎮静処置などの対応を行います。
受診のタイミングは発作の持続時間や頻度、程度によって異なります。発作が続く場合は、できるだけ早く動物病院を受診してください。ただし、発作中に抱っこしたり急いで連れてきたりするとそれが刺激になり、さらに発作が止まらなくなる可能性があります。そのため、まずは動物病院に電話するか、おさまってから連れていくようにしましょう。
診断方法
診断は、以下のような流れで実施します。
①問診
まずは飼い主様から、発作が起きたタイミングや持続時間、どのような動きをしていたか、意識の有無などを伺います。そのため、前述したように、発作時の様子を動画で記録しておくと、診断がスムーズになります。
②血液検査
代謝性疾患(低血糖や電解質、腎機能、肝機能の異常など)の有無を調べます。代謝性疾患を除外でき、おおむね月1回以上の原因不明の発作が起こるようであれば、MRI検査をお勧めしています。
③MRI検査
中枢神経の病気(脳腫瘍、脳炎、血栓、先天的な脳の異常)の有無を確認するためには、MRI検査が有効です。
当院では、必要に応じて信頼できる2次診療施設をご紹介し、スムーズにMRI検査を受けていただけるよう対応しています。
これらの検査で明確な異常が認められない場合には、「特発性てんかん」と診断し、治療を進めていきます。
治療方法
発作の治療において最も重要なのは、「重積発作を起こさせないこと」です。発作が短時間で終わり、発作の頻度も少ない場合には、経過観察のみで済むこともあります。しかし、月に数回以上の発作が見られる場合には、抗てんかん薬による内服治療が必要になります。
当院では、発作の頻度や重症度に応じて、以下のような治療を行っています。
・定期的な内服薬によるコントロール
・強い発作が何度も起きてしまう場合は頓服薬の処方
これらの治療で発作がコントロールできない場合、試験的に脳炎や脳圧を改善させるような薬を使用したりします。
それでも発作が治まらないケースでは、全身麻酔下で気管挿管を行い、人工呼吸下で半日から1日程度、脳を休めるような処置を行うこともあります。
<治療開始後の通院について>
治療開始後は薬による治療効果を確かめるために、定期的に来院いただき、現在使用しているお薬の血液中の濃度を測定します。最初のころは1か月に1回程度の通院が必要ですが、発作が落ち着いてからは、3か月ごとの通院で管理が可能です。
また、通常の薬が効きにくい場合にはサプリメントの併用や、人の小児向けに使われている抗てんかん薬を試験的に使用するケースもあります。当院では、その子の状態に合わせた治療を柔軟にご提案しています。
まとめ:発作に備え、落ち着いて行動するために
犬や猫の発作は突然起こるため、飼い主様が驚かれるのは当然のことです。しかし、事前に発作についての知識を持っておくことで、冷静な対応が可能になります。発作が短時間で治まったとしても、再発を防ぐためには適切な治療と継続的な管理が必要です。
当院では、発作に対して的確に対応できる体制を整えており、必要に応じて精密検査や高度な処置も実施しています。診察時にはできるだけ分かりやすくご説明いたします。
少しでもご不安がある方は、どうぞお気軽に当院までご相談ください。
東京都調布市の動物病院なら『タテイシ動物病院』
【当院のアクセス方法】
府中市・三鷹市・狛江市アクセス良好です。
■電車でお越しの場合
・京王線 調布駅 東口 徒歩5分
・京王線 布田駅 徒歩5分
■バスでお越しの場合
布田一丁目バス停から徒歩1分
■車でお越しの場合
調布ICから車で6分
病院隣に当院専用駐車場2台あります。
※満車時はお会計より近隣パーキング料金(上限あり)をお値引きいたします。