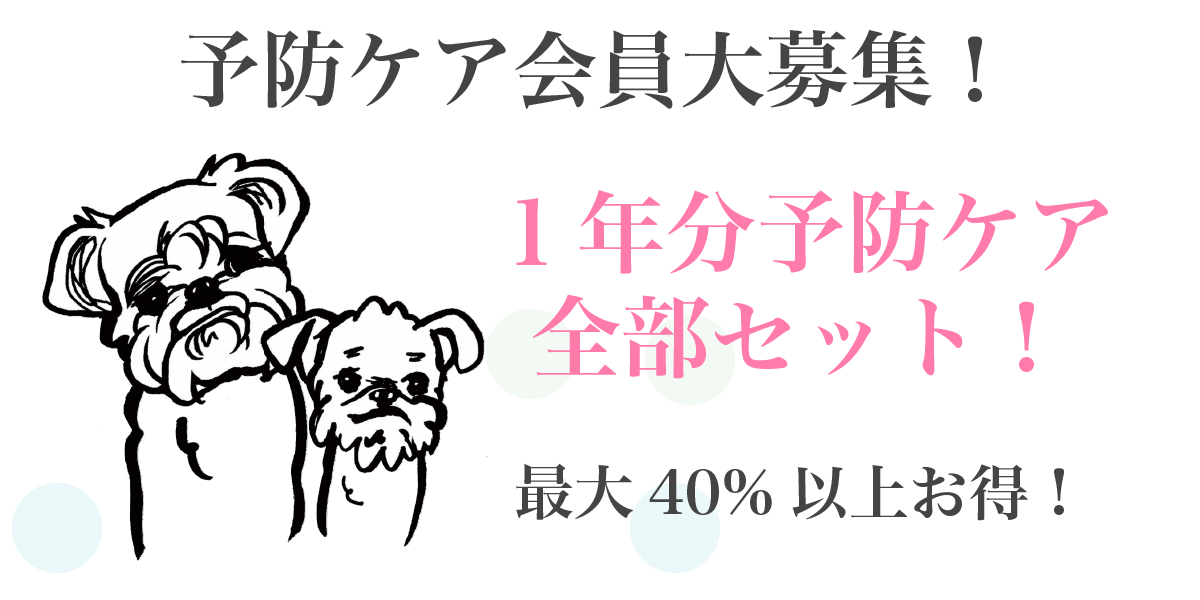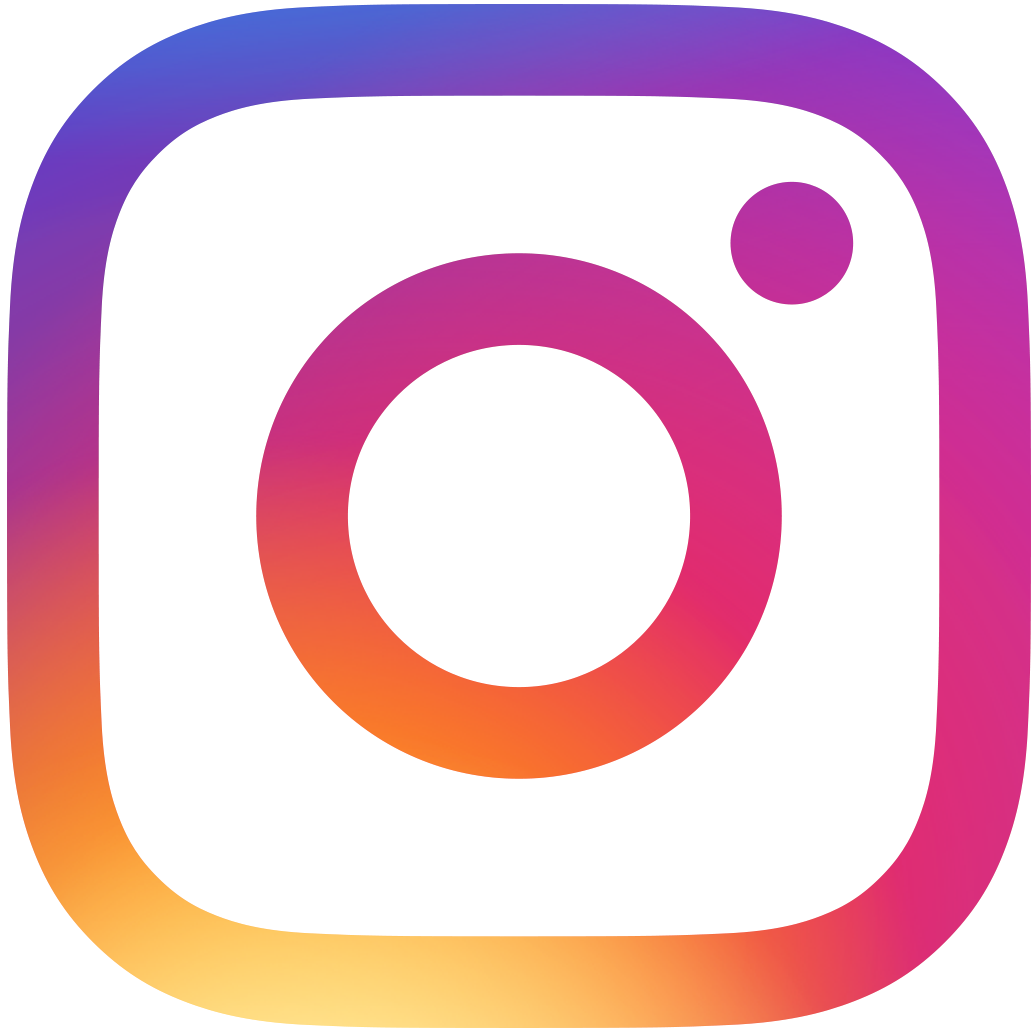「最近、愛犬が水をたくさん飲むようになった気がする」「尿量が増えたかも…?」と感じたことはありませんか?こうした変化は、年齢のせいと思われがちですが、実は病気の初期症状のサインである可能性もあります。
犬に多い多飲多尿の原因には、慢性腎臓病や糖尿病、末期の肝不全などといった病気の一症状として現れることがあります。中でも特に注意したいのが、ホルモンの異常によって起こる「クッシング症候群」です。
クッシング症候群は進行性の疾患で、放置すれば血栓や糖尿病などの重篤な合併症を引き起こす可能性があります。診断にはホルモン測定が必要ですが、当院では院内でコルチゾール(副腎皮質ホルモン)を測定できる体制を整えており、迅速な診断と治療方針の決定が可能です。
今回は犬のクッシング症候群について、症状や診断方法、治療法、そして当院の取り組みなどをご紹介します。
犬のクッシング症候群の症状と早期発見
クッシング症候群に最も頻繁に見られる症状が「多飲多尿」です。実際に、90%以上の症例でこの症状が確認されています。水をたくさん飲む、尿の回数が増えるといった変化は、見逃されがちですが、病気の発見において非常に重要なサインです。
そのほかにも、以下のような症状が見られます。
・腹部の膨らみ(肝臓が腫大することで腹部膨満に繋がります)
・左右対称性の脱毛
・太ももなどの筋肉量の低下
これらの症状はゆっくりと進行するため、「年のせいかな」と様子を見てしまいがちです。しかし、1つでも気になる症状があれば、できるだけ早く動物病院を受診することが大切です。
クッシング症候群の2つのタイプ
犬のクッシング症候群には、原因によって以下のような大きく2つのタイプに分けられます。
<下垂体性クッシング症候群>
脳にある「下垂体」という、体全体のホルモン分泌を調整する器官から、「副腎皮質刺激ホルモン」が過剰に分泌されることで、副腎が左右両方とも腫大するタイプです。
<副腎腫瘍によるクッシング症候群>
下垂体は正常ですが、副腎の片方に腫瘍ができてホルモンを過剰に分泌してしまうタイプです。腫瘍が良性か悪性かによって治療方針や予後が異なります。
当院の診断方法
クッシング症候群の診断は、以下のような検査を組み合わせて行い、総合的に判断します。
<身体検査>
多飲多尿の有無や腹部膨満、脱毛の有無、体重(特に筋肉量)の変化などを確認します。
<血液検査>
特に肝胆道系酵素(GPT、ALP、GGT)やコレステロール値を確認します。クッシング症候群の場合、これらの数値が高くなる傾向があり、診断の重要な手がかりとなります。
<エコー検査>
副腎のサイズ(正常の小型犬で3~7mmの厚さ)や構造を詳細に評価します。左右両側の副腎が腫大していれば下垂体性、片側のみの場合は副腎腫瘍が疑われます。
<ホルモン検査(ACTH刺激試験など)>
クッシング症候群の確定診断には、血液中のコルチゾール濃度の測定が不可欠です。
当院では、ホルモン検査を外部機関に依頼せず、院内で実施できる体制を整えています。そのため、結果を待つ時間がなく、検査当日に診断と治療のご相談まで進めることが可能です。
治療方法
治療はどちらのタイプであっても、基本的には内科的治療が中心となります。
具体的には、副腎皮質ホルモン(コルチゾール)の過剰な分泌を抑える薬「トリロスタン」を使用します。
この薬は、コルチゾールの分泌をコントロールするために、生涯にわたり投薬が必要となります。また、タイプによって薬の効き方や必要な用量が異なるため、定期的に血液検査を行い、ホルモン値を確認しながら調整していきます。
なお、副腎腫瘍が原因の場合で、薬に十分な効果が見られない場合には、副腎の外科的切除を検討することもあります。特に「悪性腫瘍(褐色細胞腫や副腎腺癌)」である場合には、内科療法では対応しきれないこともあり、早期の手術が必要になるケースもあります。
治療における重要な注意点と合併症
クッシング症候群は、薬でホルモンバランスを適切にコントロールできていれば、長期にわたって安定した生活を送ることができる病気です。しかし、治療を自己判断で中断したり、投薬の間隔をあけてしまったりすると、以下のような重大な合併症が生じる可能性があります。
・血栓症
・糖尿病
・脂質代謝異常による胆管、胆のう閉塞や破裂
・免疫力の低下による重篤な感染症
犬の糖尿病の当院で行っている診断や治療方法についてより詳しく知りたい方はこちら
今までにクッシング症候群のコントロール不良により糖尿病に進行したケース、後ろ足に血栓ができ進行して足の壊死を引き起こした症例も経験しています。こうした深刻な事態を避けるためにも、獣医師の指示に基づいた投薬管理と、定期的な通院が何よりも大切です。
予後と長期管理
前述したとおり、適切な投薬管理と定期的なホルモン検査によってコルチゾールの値を安定させることができれば、多くの犬は通常の生活を問題なく送ることができます。特に下垂体性タイプでは、内科治療に良好に反応するケースが多く見られます。
一方、副腎腫瘍によるタイプで、腫瘍が悪性である場合には注意が必要です。転移や急激な悪化が見られることもあり、早期の外科的治療が予後を大きく左右します。
当院では、継続的な検査と管理体制を整え、愛犬が長く健やかに過ごせるようサポートしています。なにか分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください。
予防と早期発見のために
ご家庭での観察が早期発見の鍵を握ります。日常の中で水を飲む量や尿の回数を意識して記録しておくことで、小さな変化にも気付きやすくなります。
また、クッシング症候群は中高齢の犬に多く見られる病気です。特に中年齢を過ぎた頃からは、年に2回の健康診断を受けることをおすすめします。なかでも一般的な血液検査で確認できる肝臓や胆道に関わる酵素、コレステロール値の変化は、クッシング症候群の早期発見につながる大切なサインとなることがあります。
ご家庭と動物病院の両方で健康状態をチェックすることが、病気の早期発見と治療の成功につながります。
まとめ
クッシング症候群は、下垂体性と副腎性という2つのタイプに分かれ、それぞれで診断方法や治療方針が異なります。どちらの場合も、早期に発見し、的確な内科治療を始めることが大切です。特に「多飲多尿」は見逃してはならない初期サインです。
当院では、院内でのホルモン測定体制を整備しており、検査から診断、治療開始までをスピーディーに対応可能です。さらに、長期的な薬物管理や合併症予防のための定期チェックも重視しています。
もしも愛犬の飲水量や排尿の変化に気付かれた際には、どうぞお気軽に当院までご相談ください。飼い主様と一緒に、愛犬の健康を守るお手伝いをさせていただきます。
★ご予約は下記のLINE予約フォームから!★
東京都調布市の動物病院なら『タテイシ動物病院』
【当院のアクセス方法】
府中市・三鷹市・狛江市アクセス良好です。
■電車でお越しの場合
・京王線 調布駅 東口 徒歩5分
・京王線 布田駅 徒歩5分
■バスでお越しの場合
布田一丁目バス停から徒歩1分
■車でお越しの場合
調布ICから車で6分
病院隣に当院専用駐車場2台あります。
※満車時はお会計より近隣パーキング料金(上限あり)をお値引きいたします。