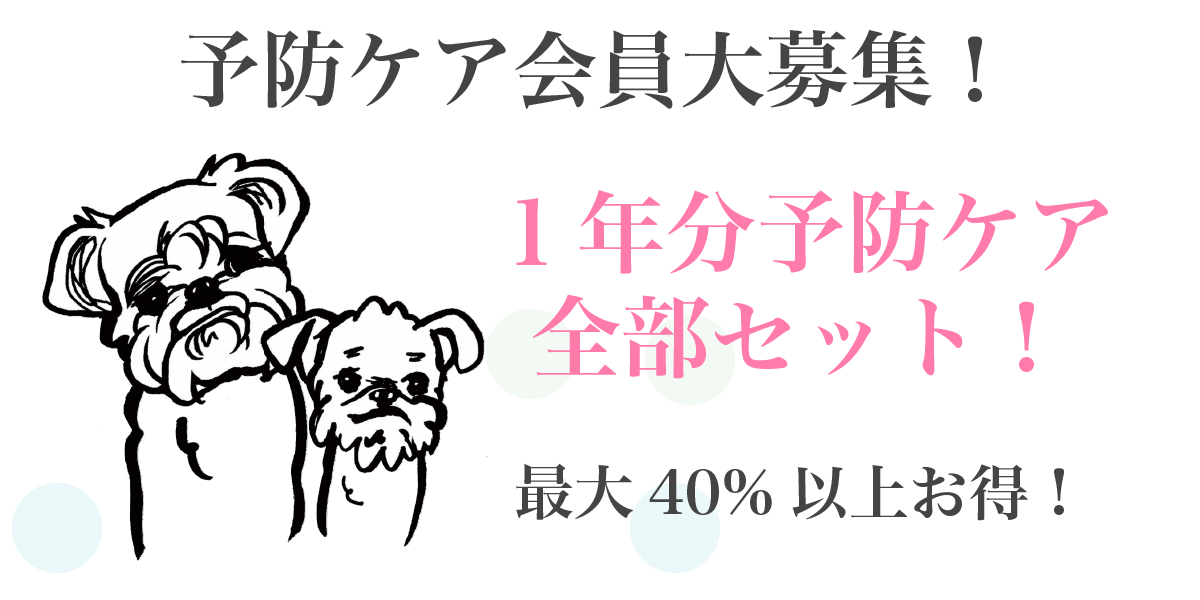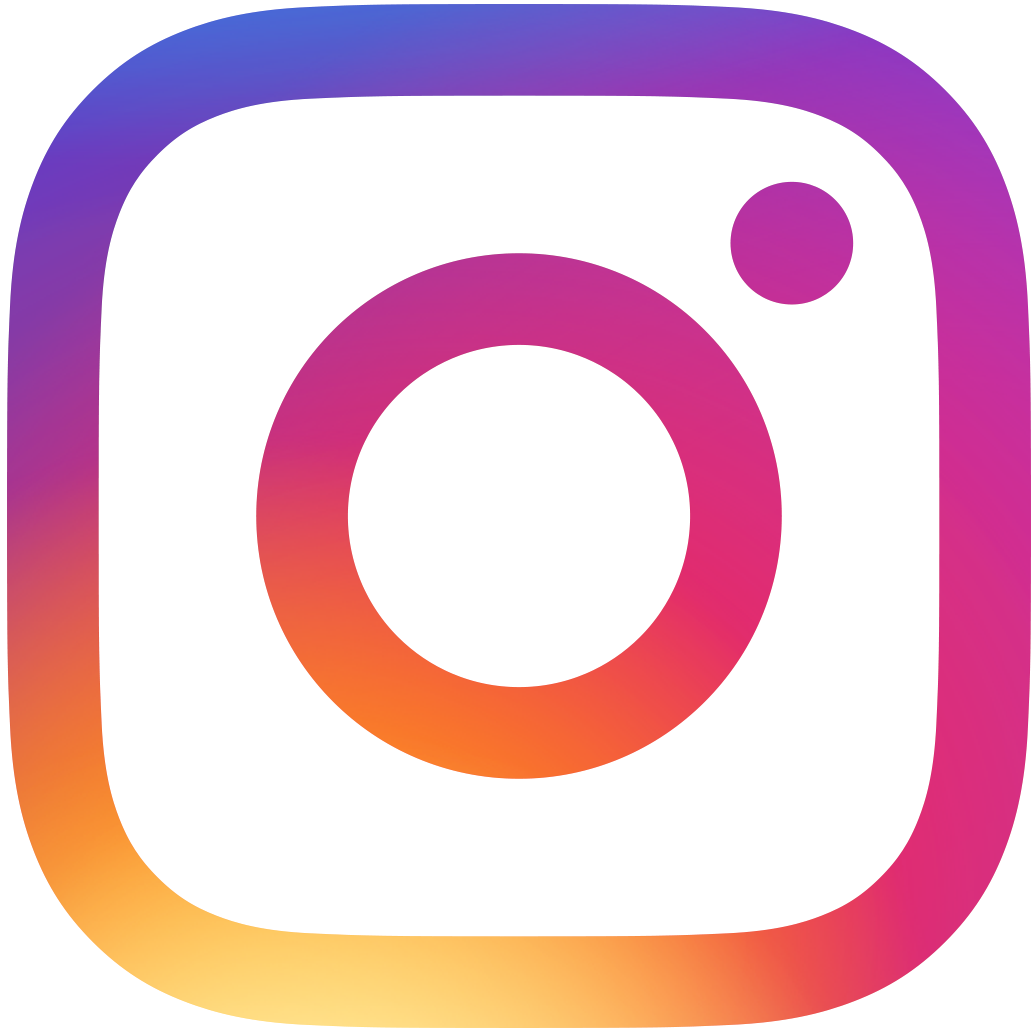愛犬や愛猫が「最近なんとなく元気がない」「食欲が落ちてきた」そんな様子を見て、不安になったことはありませんか?実は、それらの症状は膵炎という病気のサインかもしれません。
膵炎は、膵臓という消化と血糖値をコントロールする重要な臓器に炎症が起こる病気です。犬と猫どちらにも発症する可能性があり、特にどちらが多いということはありません。膵炎の初期症状は見逃しやすく、重症化すると命に関わることもあるため、早期発見と迅速な治療が大切です。
今回は犬と猫の膵炎について、症状や動物種ごとの特徴、診断、治療、予防方法などを詳しくご紹介します。
膵炎とは?
膵臓は、胃や十二指腸の近くに位置している臓器で、食べ物の消化を助ける酵素を分泌しています。これらの酵素は、タンパク質や炭水化物、脂肪を分解するうえで重要な役割を果たしています。通常、膵臓はこれらの消化酵素を膵管という通り道を通って、十二指腸に送ります。しかし、何らかの原因によって酵素が膵臓内で活性化されてしまうと、膵臓に炎症が起きる「膵炎」という病気を引き起こします。
膵炎は、進行のスピードや症状の現れ方によって「急性膵炎」と「慢性膵炎」の2つのタイプに分類されます。
<急性膵炎>
嘔吐や下痢、食欲の低下などの症状が急に現れ、早めの対処が必要になることが多いのが特徴です。
<慢性膵炎>
ゆっくりと炎症が進むため、症状が軽くて見過ごされやすい傾向があります。ただし、気づかずに放っておくと、膵臓に長期間ダメージを与えてしまうこともあるため注意が必要です。
犬の膵炎の特徴
犬では、膵臓から漏れ出した消化酵素によって膵臓自体とその周囲の組織に炎症が波及します。これにより、十二指腸などの消化器系全体の動きが悪くなり、下痢や嘔吐、腹痛、元気消失といった症状が現れます。さらに症状が進行すると、全身の臓器に影響を及ぼし、ショック状態に陥ることもあります。
犬では「急性膵炎」が比較的よく見られ、食事やストレス、基礎疾患が引き金になるケースも少なくありません。
また、大型犬や胴長犬種(ダックスフンド)に比較的多く見られ、エコー検査によって初めて膵炎が見つかるというケースも見られます。
猫の膵炎の特徴
猫では膵炎単独で起こることもありますが、より多く見られるのが「三臓器炎」という病態です。これは膵炎の他に、胆管や消化管にまで炎症が広がり、膵炎や胆管炎、炎症性腸疾患が同時に起こります。三臓器炎を引き起こす原因は今のところ解明されていませんが、猫特有の消化器の構造が関係していると考えられています。
三臓器炎では犬の膵炎のような消化器症状だけでなく、黄疸(目や口の粘膜が黄色くなる)や食欲不振、体重減少など、より全身的な症状が現れることがあります。
診断方法
膵炎は見た目だけではわかりにくいため、正確な診断には以下の2つを中心に検査を実施します。
<エコー検査(超音波検査)>
エコー検査は、最も信頼性の高い検査方法です。この検査では、膵臓の大きさや周囲の脂肪組織の変化、十二指腸の壁の厚みなどを細かく評価することで、炎症の程度や広がりを把握できます。検査中は犬や猫への負担を最小限に抑えながら、丁寧に状態を確認します。
<血液検査>
血液検査では炎症の有無を調べるために、CRPやSAAといった炎症マーカー(炎症に反応して数値が上がる項目)、や膵臓に由来するリパーゼと呼ばれる酵素を測定します。ただし、これらの数値は膵炎以外の消化器疾患でも上昇するため、血液検査だけでは確定診断できません。そのため、エコー検査との併用によって、より正確な診断が可能になります。
治療方法
膵炎の治療は、内科療法で炎症の抑制と体の回復をサポートすることです。
膵炎の犬や猫は消化管の動き(蠕動運動)が低下していることが多いため、内服薬が十分に吸収されず、場合によっては嘔吐を誘発してしまいます。そのため、初期治療では静脈注射による投薬が基本となります。
重度の場合は入院して集中的に管理する、あるいは毎日通院して治療を進めていく必要があります。
<点滴治療の内容>
特に治療には点滴が不可欠です。点滴は、脱水の改善や消化管の蠕動運動を促す薬(蠕動改善薬)、胃酸の分泌を抑える制酸剤、炎症を和らげる抗炎症剤などを含め、総合的に投与していきます。
<術後の食事管理>
状態がある程度落ち着いた後は、少しずつ食事療法に切り替えていきます。以前の膵炎の治療では完全絶食が推奨されていましたが、現在では胃腸の動きが回復次第、少量ずつ食事を与えた方が望ましいとされています。
経過と注意点
膵炎は軽度であれば比較的早く回復しますが、重度になると命に関わる場合もあります。特に、ぐったりして立てなくなっている、ショック状態などが見られる場合は非常に危険な状態です。こうした症状が現れる前に、できるだけ早く治療を開始することが重要です。
また、一度膵炎を発症した犬や猫はその後、再発する可能性が高まります。そのため、治療が終わったからといって安心せず、定期的な健康チェックを継続していくことが重要です。
予防と管理
膵炎の予防には、日頃の食事管理が大切です。脂質の多い食事や、消化の悪いフードは膵炎のリスクを高めるため、避けるようにしましょう。また、「体によくなさそうなフード」、特に安価で栄養バランスが悪いフードは控えることをお勧めします。
ほかにも、定期的な健康診断も再発予防には欠かせません。当院では、年に1回の血液検査で、膵臓機能や肝機能、タンパクやグロブリン値などのバランスを丁寧にチェックし、異常があればすぐに対応できる体制を整えています。
まとめ
犬や猫の膵炎は初期症状が目立ちにくいため、発見が遅れがちな病気です。しかし、進行すると命に関わる重篤な状態になることもあります。そのため、早期に発見し、適切な治療をすることが、回復のカギとなります。
愛犬や愛猫の「様子がいつもと違う」と感じたときは、迷わず動物病院を受診してください。大切な家族の命を守るために、早期発見・早期治療、そして日頃からの健康管理を心がけていきましょう。
■関連する記事はこちらから
東京都調布市の動物病院なら『タテイシ動物病院』
【当院のアクセス方法】
府中市・三鷹市・狛江市アクセス良好です。
■電車でお越しの場合
・京王線 調布駅 東口 徒歩5分
・京王線 布田駅 徒歩5分
■バスでお越しの場合
布田一丁目バス停から徒歩1分
■車でお越しの場合
調布ICから車で6分
病院隣に当院専用駐車場2台あります。
※満車時はお会計より近隣パーキング料金(上限あり)をお値引きいたします。